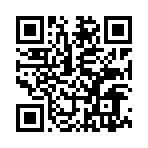2012年05月27日
ちいさな企業の未来
メンバーのみなさん、ごきげんよう。
今月は決算書作成でバタバタだった中川です。
ワタシは4月から積極的に対外的な勉強会に参加してるんですが、なんとなく申込をしていたら活用塾を含め週2位のペースになってしまい本業がヒマで本当に良かったな…と思っています。(イヤ、よくね~だろ!)
今日は経済産業省の主催する中小企業応援プロジェクト”ちいさな企業”未来会議にオブザーバー参加をしてきました。

会議に参加される企業はワタシも何社か見聞きして知っているような県内で活躍している企業の代表者さん達で、以下の3つのテーマについて意見を交換し合うものでした。
1.国政における中小企業支援政策の成果と課題
2.次代を担う若手・青年層、女性の活力発揮
3.「地域」の中の中小企業
”ちいさな企業”未来会議ではこのような地方会議で寄せられた意見を集約して、それらをタタキ台にして今後の中小企業支援を検討していくみたいです。
ワタシもアンケートに意見をだしておきました。(中小企業庁さん、ちゃんと読んでくださいね。)

会議の話合いを聞いていてかなり(本当に)イロイロなことを考えました。
賛同するところもあれば、意見が異なることもあり、情報を整理してハラに堕としておかねばイカンと思います。
特に感じたことは後継者問題です。
二代目と呼ばれる方々の担い手がいないのは、中小企業であればどんな業種であれ大きな問題となっているそうです。
まぁ、継いでくれる人がいなければ中小企業は無くなっちゃいますからね。
でも、先代の気持ちもあるんでしょうが、事業って単純に次代に引き継ぐのが良いのか悪いのかワタシには判りません。
下の図はワタシのイメージなんですが、事業を始めた時(先代)は3つの要素の上下が大体一致していたと思います。
しかし二代目に各要素について共感を得られなければ「なぜ、オレが?」って気分になりませんかね?

つまりその下の抱えているモノを処分/維持することを担え、と言われても自身にとってプラスのものが多ければ良いでしょうが、今の時代、マイナスのモノが多いと思いますし、押しつけられても困ってしまうと思います。
事業の引継には「守るべきモノ」があれば、それを脈々と受け継ぐ仕組みが必要になってくると思います。
または、あくまでイメージですが守るための「代替のもの」を用意してあげれば別のカタチで事業は存続できるかも知れません。
この辺りは今後、事業承継やM&Aの手法を取り入れた新たなビジネスになる感じもしますが、何よりも「後継者」ってのは勝手に生まれるモノじゃありません。
事業を行う者としては事業が軌道に乗った時点で、世の中にどんどん貢献していくのと併せてどうやって存続させていくのかを考えなければいけないな~と痛感しました。
ナカガワ
今月は決算書作成でバタバタだった中川です。
ワタシは4月から積極的に対外的な勉強会に参加してるんですが、なんとなく申込をしていたら活用塾を含め週2位のペースになってしまい本業がヒマで本当に良かったな…と思っています。(イヤ、よくね~だろ!)
今日は経済産業省の主催する中小企業応援プロジェクト”ちいさな企業”未来会議にオブザーバー参加をしてきました。

会議に参加される企業はワタシも何社か見聞きして知っているような県内で活躍している企業の代表者さん達で、以下の3つのテーマについて意見を交換し合うものでした。
1.国政における中小企業支援政策の成果と課題
2.次代を担う若手・青年層、女性の活力発揮
3.「地域」の中の中小企業
”ちいさな企業”未来会議ではこのような地方会議で寄せられた意見を集約して、それらをタタキ台にして今後の中小企業支援を検討していくみたいです。
ワタシもアンケートに意見をだしておきました。(中小企業庁さん、ちゃんと読んでくださいね。)

会議の話合いを聞いていてかなり(本当に)イロイロなことを考えました。
賛同するところもあれば、意見が異なることもあり、情報を整理してハラに堕としておかねばイカンと思います。
特に感じたことは後継者問題です。
二代目と呼ばれる方々の担い手がいないのは、中小企業であればどんな業種であれ大きな問題となっているそうです。
まぁ、継いでくれる人がいなければ中小企業は無くなっちゃいますからね。
でも、先代の気持ちもあるんでしょうが、事業って単純に次代に引き継ぐのが良いのか悪いのかワタシには判りません。
下の図はワタシのイメージなんですが、事業を始めた時(先代)は3つの要素の上下が大体一致していたと思います。
しかし二代目に各要素について共感を得られなければ「なぜ、オレが?」って気分になりませんかね?

つまりその下の抱えているモノを処分/維持することを担え、と言われても自身にとってプラスのものが多ければ良いでしょうが、今の時代、マイナスのモノが多いと思いますし、押しつけられても困ってしまうと思います。
事業の引継には「守るべきモノ」があれば、それを脈々と受け継ぐ仕組みが必要になってくると思います。
または、あくまでイメージですが守るための「代替のもの」を用意してあげれば別のカタチで事業は存続できるかも知れません。
この辺りは今後、事業承継やM&Aの手法を取り入れた新たなビジネスになる感じもしますが、何よりも「後継者」ってのは勝手に生まれるモノじゃありません。
事業を行う者としては事業が軌道に乗った時点で、世の中にどんどん貢献していくのと併せてどうやって存続させていくのかを考えなければいけないな~と痛感しました。
ナカガワ
この記事へのコメント
中川さん、積極的に勉強をされているようでとても感心します^^
中川さんもいずれは会社の後継者になる身だと思いますので、このような勉強はとても大事なことですよね。
きっと、その努力は報われますよ。
型にはまらず、よいものは継承し、改善すべきは改善して、良い意味で個性のある経営者を目指して下さい!
中川さんもいずれは会社の後継者になる身だと思いますので、このような勉強はとても大事なことですよね。
きっと、その努力は報われますよ。
型にはまらず、よいものは継承し、改善すべきは改善して、良い意味で個性のある経営者を目指して下さい!
投稿者(FPハマちゃん)) at 2012年05月28日 08:12
浜崎さん、ありがとうございます。
外部から情報収集をしていくにつれ、地域・業種的に私達の場合は会社どころか”板金加工”業自体が失われる懸念もあります。
そこで働く人間が職を失うことを考えると恐ろしいことですよね。
結局は自由競争が支配する世界ですから、競争力ある板金加工業を地域にもたらす方法を当事者同志で考えないといけないんじゃないかな、と最近強く思います。
ナカガワ
外部から情報収集をしていくにつれ、地域・業種的に私達の場合は会社どころか”板金加工”業自体が失われる懸念もあります。
そこで働く人間が職を失うことを考えると恐ろしいことですよね。
結局は自由競争が支配する世界ですから、競争力ある板金加工業を地域にもたらす方法を当事者同志で考えないといけないんじゃないかな、と最近強く思います。
ナカガワ
投稿者(遠州工機@中川) at 2012年05月28日 08:24
中川さんお疲れ様です!
中小企業って難しいですよね(´・_・`)
ましてや日本人ってビジネスに徹するってより、会社に対する感情や愛着が強く、、それが代替わりの時に本来冷静に考えたらそうすべきでない選択をしてしまいがちですよね。
守るもの手放すものをしやすくなるように、もっと緩やかにM&Aとかが出来る法をふくめた環境整備がされればなっと切実に感じてます。。
中小企業って難しいですよね(´・_・`)
ましてや日本人ってビジネスに徹するってより、会社に対する感情や愛着が強く、、それが代替わりの時に本来冷静に考えたらそうすべきでない選択をしてしまいがちですよね。
守るもの手放すものをしやすくなるように、もっと緩やかにM&Aとかが出来る法をふくめた環境整備がされればなっと切実に感じてます。。
投稿者(海野勝人) at 2012年05月28日 10:43
海野さんの言うとおりですね。
中小企業は企業と個人(社長)が切っても切れない関係にあるのに、会社という体を為しているところにこういった矛盾を含有しています。
良く言えばそれが「日本的」であり、対顧客=対人でビジネスが成り立ち得る関係です。
しかし、それには「人(人物)」に依るところが大きくそこが事業承継の際に足かせになってくるところでしょう。
この問題は必ず来ることなので対処は可能な問題でもあります。
やはり必要なのは当事者同志の一体感、この前武藤さんが教えてくれた共感、共振の考え方にヒントがあるのかな~と思います。
ナカガワ
中小企業は企業と個人(社長)が切っても切れない関係にあるのに、会社という体を為しているところにこういった矛盾を含有しています。
良く言えばそれが「日本的」であり、対顧客=対人でビジネスが成り立ち得る関係です。
しかし、それには「人(人物)」に依るところが大きくそこが事業承継の際に足かせになってくるところでしょう。
この問題は必ず来ることなので対処は可能な問題でもあります。
やはり必要なのは当事者同志の一体感、この前武藤さんが教えてくれた共感、共振の考え方にヒントがあるのかな~と思います。
ナカガワ
投稿者(遠州工機@中川) at 2012年05月28日 15:01